永遠の高校生
1
四十歳を過ぎた城山丈吉だったが
心は高校生のままだった
丈吉は夜の学校に忍び込み
校庭に
名も知らぬ植物の苗を埋めた
四十歳を過ぎた記念に
植樹をしたかったのだ
土に苗を埋め
まわりを踏み固めて
じょうろを取り出して水を注いだ
するとそれまで萎れていた植物が
みるみる息を吹き返した
垂れていた枝は上を向き
閉じていた葉が開いた
枝はするすると伸びて
丈吉の鼻先に達し
小さな蕾から花が開いた
花の香りを吸い込み
丈吉は大きくむせた
くしゃみも止まらなかった
でも丈吉の心は晴れていた
いつかこの苗が大木となるとき
俺はきっと
一歩踏み出せるのではなかろうか
どこに踏み出すのかは知らぬが
それはまさに
偉大な一歩となるだろう
丈吉の胸は希望に震えていた
2
屋上の柵を乗り越えて
丈吉は夜の校庭を見下ろした
昔はここから飛び降りられるような
気がしたものだ
今もそんな気がする
どこか遠くで
犬の吠える声がした
風も鳴っていた
丈吉は屋上のへりから
目の前の
何もない空間に歩き出した
手を大きく上下に動かすと
体は宙に留まったままだった
丈吉は手の動きを抑え
ゆっくりゆっくり高度を下げて
校庭に下りて行った
つま先が校庭の土に触れた時
丈吉はそこを蹴り
ふたたび舞い上がった
高く高く登り
夜の街を空から眺めた
家々の窓には
ぼんやりと灯りがともり
街路灯は点いていたが
街に人影は無かった
風が吹いていた
丈吉は詰襟の学生服をなびかせ
夜の街の上を
いつまでも飛び廻った
3
下駄箱が立ち並ぶ
向こう側の暗がりを
なにやら得体の知れないものが
通り過ぎた
丈吉は下駄箱の蓋をいくつか開けてみたが
中はみな空だった
しかしいくつ目かの箱の中に
小さな封筒が置かれているのを発見した
丈吉はその
色あせた封筒を取り出した
手で砂とほこりを払い
小さく折り畳まれた手紙を取り出した
変色した紙のうえに
釘のような文字で
「ずいぶんおそかったね」
と書かれていた
4
丈吉は真っ暗な校庭で
犬と遊んでいた
手に何も持たず
それを遠くに投げる動きをすると
犬は喜んで走り去り
何か咥えて
戻ってくる動作をした
丈吉と犬は
何度もその行為を繰り返した
そしてひときわ大きく振りかぶり
遠くに投げる動きをすると
犬は
それまでより早いスピードで走り去り
二度と戻って来ることがなかった
5
四十歳を過ぎた丈吉は部屋に戻り
学生服を脱いでノートを広げた
机の隅の鉛筆削りをひとしきり回し
丈吉はノートに書きはじめた
「俺はもうすべてを学び尽くした」
「それなのに何も知らない」
しばし手を止めて丈吉は考えた
「はじめから」
と彼は書き続けた
「学べることなど何も無かったんだ」
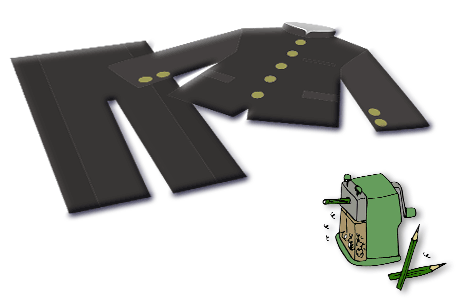
 しんぞうの創作室
しんぞうの創作室 

